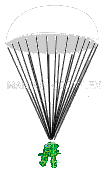
**maniac+complex**
VOTOMS WONDERLND
「装甲騎兵ボトムズ
俺的図書館」
オリジナル小説
「月光」
P9
「月光 第9話(蜜月終了)」
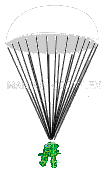
**maniac+complex**
VOTOMS WONDERLND
「装甲騎兵ボトムズ
俺的図書館」
オリジナル小説
「月光」
P9
「月光 第9話(蜜月終了)」
現実に戻った彼の隣で、彼女は月光を絡め取るリングを見ていた。 それは、いつもそれを見つめる彼女がそうであるように、何か言いたそうだった。 だがその唇は動かず、彼には何も聞こえない。 それが悔しかった。 何も分からない・・・彼女の考えている事が! 切ない彼は、思い余って聞いた。 「何か・・・特別な意味でもあるのか?」 「え?」 その問いに女は一瞬意味が分からないという風に表情を変えたが、男の視線を感じると、すぐに普段どおりの微笑をみせた。 「別に・・・すごく嬉しかっただけ。」 そしてリングを弄ぶと、そのまま目線を落とし、彼に話しかける。 「あたし、おかしいかな?」 「え・・・・?いや・・・。」 彼はうろたえた。彼の考えには根拠など無いのだ。 今も、ただ彼女の様子を見ていて思わず口から出ただけで。 それがわかっているのか、女は続けた。 「あなたに貰ったものなら何でも嬉しい。前に貰った花も、こないだ書いてくれたメモも、何でもとっておいて眺めてるの。」 「・・・メモ?あの・・・ただの紙をか?」 「・・・そう!」 彼は予想もしなかった事実に過去の遺物を思って眉をしかめたが、彼女はそんな男を構いもせずに声を弾ませ、無邪気な愛らしさで彼の首に抱きつく。 「形に出来ないものも、出来るものも、全部。とっておくの。」 女の口調は夢見るようだった。 その軽やかな言葉は、あと少し力を加えるだけでそのまま空へ逃げてゆきそうで。 それに比べたら、自分の言葉なんて掘りおこしたばかりの石のようだ、と彼は感じた。 鈍重で、無骨で、気が利いてなくて。 だが、彼はもう知っていた。 言葉だ。 自分の気持ちを伝えるには、言葉が必要なだと。 男はやっとの思いで口をひらいた。 「いや、でもそれならもっとマシなのを・・・。」 「いいの。」 彼の必死の言葉はあっけなく遮られた。 驚く彼が彼女を見ると、顔を上げた彼らの目が合い、見つめる瞳に互いの姿が映る。 「だって、あたしの為にあなたが・・・くれたのよ?それだけで嬉しい。」 「あ、・・・ああ。」 男はどうしてよいか分からず、しかし、とりあえず返事を返す。 それに満足したのかしないのか、女はにっこり微笑むと再び姿勢を戻し、今度は彼にもたれかからずに、一人で座る。 男はその距離をいささか気にした。 そして、沈黙はしばらく続いた。 女はまたも何処か遠くを見ながらリングを弄び、男はそんな恋人を横目で見つつ、新しい疑問で頭を満杯にしていた。 『何をする?そんなものを集めて、どうするのだろう?』 女は収集癖があるようには見えなかったし、二人の部屋を考えてもそれが何処に仕舞ってあるか、男には見当もつかなかった。 そして、彼らの荷物は常にトランク一つである。 ・・・では、何故? 何の為に、2人の結び付きを残すのだ? だが、その答えはその場では出なかった。 そんな意味で、彼はまだ幸福だったのである。 「・・・ねえ。」 その沈黙は女の言葉で破られた。 場を持たせきれなかった男は、いささかほっとして動作で返事をする。 触れたいものに触れられないでいた左手で向き合った女の頬に触れると、もっと顔が見えやすいように自らの方に動かした。 これでやっと彼女の目が見れる。 「あたしと一緒で無い時も、あたしの顔を思い出せる?」 「・・・え?」 いつもそうだが、今夜の彼女には彼は驚かされてばかりだった。 「それは何を・・・?」 「ねえ、どう?」 いつもながら、彼が言葉に詰まっている隙に、彼女の思考はすっかり先に進んでいた。 だが、彼女は何故か不安げに彼を見つめている。 「あ・・・。」 男は返答に困った。 これまでうかつに返事をしてかなり彼女を怒らせた彼は、もうそんな失敗はしたくない、と、こんな時はいつも慎重だ。 「・・・もしかして、忘れちゃってるの?」 だが、待ちきれない女は口を開いた。 こんな時、男は焦る。 女はどうしてこんなに人の気持ちを確かめたがるのだろう。 そんなものは決まっているというのに。 そうして、男はイヤでも女との性の違いを思い知る事になるのだ。 彼は「口に出す」という作業がどんなに大変な事なのかをいつか彼女に知らせようと常に心に誓っていたが、それは未だ実行されずにいた。 男は、まず彼女の髪に触れ、心を落ち付かせた。 彼女の髪は本当になめらかで、もっと指に留めておきたいという彼の意思に反して、指を滑り落ちてしまい、それの繰り返しは、彼を虜にする。 まるで動物の本能のように。 本能。 そう、本能だ。 男は本能的に女を求め、その姿を探す。脳裏に刻む。それの繰り返しな日々だ。 決して忘れる事などは無い。 「忘れない。離れている時の方が、俺は・・・。」 いつもの言葉だ。滑らかに出ない。 これで良かったのだろうか。 無言で下を向いた彼女を見て、またも気がきかない言葉を発したのだと感じた男は黙りこくってしまった。 だが、女は男とは違う音を聞きとっていた。 彼女は言葉少なな彼の本当の意思を聞きたいと、常に思っていた。 それは恋に脅えてる心や、恋の熱にうなされる熱病患者のようなうわごとではなく、彼の心から自然に溢れる歌声である。 この男は言葉の使い方というものを全くわきまえていなかった(それは本人も自覚しているらしいが)。 彼の言葉はいつも曖昧で、説明不足なのだ。 もう少しで喉から出そうな言葉をとどめているような切れの悪さと、恋をしているという事を必死に隠そうとする可愛らしい心で自分の音量を抑えてしまっている。 会話自体に馴れていない事も原因だったが、ほとんどはそんな自分が信じられないという、恋へのとまどいであろう。 だが、彼の心を離れ、そのとまどいから無事に逃げおおせた数少ない音が届く度、それは彼女の心をくすぐる。 それが到達するのは耳ではなくて、何かが手を入れてねじ込んできたような強引さで彼女の臓器を掴み取るのだ。 そうすると、恋人の前では冷静でいようと思っている彼女の心は途端に恋に捕らわれてしまう。 その度に女は確信する事になるのだ。 やはり、この男しかいない。 今更どうなるものでもないが、女の心は決まっていた。 愛を与えよう。 ありったけの愛を、今のうち。 それしか出来ない、と。 「ありがとう。」 沈黙の後、女はそう言って男を見上げた。 そこには制御出来ない恋心に戸惑いながらも答えを見付けようとしている若い瞳があった。 意識していなかった行動によって不安に陥ったらしい事に気がついて少しばかりの罪の意識と・・・彼の心がわかったようで、女は少しこそばゆさを感じていた。 男の瞳は彼女の答えを求めていた。 女は微笑む。「困らせてごめん」と心で呟いて。 女の笑顔を見て、彼の顔もほころぶ。 そんな彼は、普段とは違って年齢に応じた幼さを見せる。 それが彼女は好きだった。 「絶対に忘れちゃイヤよ。約束して。」 首をかしげて甘える恋人の仕草に、男は胸の高鳴りと幸福感を露にした。 今度は彼女にヒントを貰っていたので、言葉もすらすら出てきた。 「・・・約束する。」 小さな声で言う。 「ずっと、忘れない?遠くても?」 女は声のトーンを上げて言うが、男は大きく頷いた。 「ずっと、何があっても・・・。」 男の呟きは、まるで呪文だった。 言葉にする事によって自分に暗示をかけ、もっと深い心に酔いう。 恋という魔法は、機械に侵された男すらも溶けるような力を持つのだ。 「あたしも忘れない。ずっと・・・。」 うるんだ瞳はなんの意味であろう? 物事には表に出すべきものと、そうでないものがある。 その口から出てくる言葉以外にも沢山のものを飲み込んで、女は言葉を紡ぐ。 その恋は余りにはかないから、そして・・・。 男の腕に力が入って二人の距離を縮め、恋人同志では当たり前の仕草で唇が重なった。 全身で相手の体を感じようと、腕が動く。 柔らかい肌の上を這う男の唇に小さく反応して、女は腕の力を強める。 既に自由になった唇からは絶え間なくため息が漏れて、結果的に男の動きを誘った。 男は丹念に唇を使い、彼の唇が女の首を経て胸元に下がる頃には、 女の頬を上気させ、男の体にもたれかかっているのが精一杯な状態にする事に成功していた。 女の息が荒い。 男の心は動いた。 彼女を愛したい。 この手で変えてみせたい。 男は迷わず、いつものように女の服に手をかけた。 それは不思議な体験だった。 普段なら危険を感じて無防備な体制は取らない男である。 だが壁の無い場所でのその日の行為は警戒心よりも開放感を誘い、男が女の口を抑える事もしなかった。 少しばかりのシーツとなった上着はとうにはみ出して足を草の汁で汚し、2人は愛を確認する。 (だが男は女の頭を守る事だけは忘れなかったが) ついさっき愛し合ったばかりだというのに、2人の欲望は留まる事を知らない。 肌を通して伝わる感情に彼らは酔っていた。 自分の手で女が乱れるという事実は、彼だけが知っている姿である。 その権限を他人に渡す事は絶対に耐えられなかった。 そして、女が受け入れるのも彼だけだった。 女は、受け入れる人間がいるという喜びを男に与えた。 愛、というものだろうか。 2人は欲望に身を任せて肉体を振るわせる。 この感覚、これこそが充実感である。 かけがえの無い力を使い、相手を満足させようとやっきになる滑稽な姿こそ、 唯一の相手への奉仕ではなかろうか? 欲望も、相手によっては力をなさない。 それは間違い無かった。 「疲れちゃった?」 2人は再びここに来た時のような見た目だったが、それは全く違っていた。 男のシャツは下敷きにされた事によってひどく汚れ、まるで一日草むらで遊んできたようである。 2人とも男女が愛し合った後にありがちな虚脱感と深い密着度に包まれて、そして女の胸元には先ほどまでには無かった赤い痕跡があった。 とうとう一睡もしなかった二人は今、白む空の下でまどろんでいる。 座った女の腿に頭を乗せ、男は夢と現実とを行ったり来たりしていたのである。 早起きな鳥の声が聞こえる。 周りの草は、今も落ちそうな朝露を含んで頭をもたげている。 こんな世界にいる二人は、まるで世界に彼らしか存在していないかのように不自然だ。 生き物には夜と目覚めが存在したのに、彼らの眠りは無かった。 だが、一晩中愛を交わした男と女にも休息が必要だろう。 夜明けが近づいた。 人間の日常が始まる。 朝の気配と食事の仕度の匂い、車の音、話し声に包まれた世界が目を覚ますのだ。 男はぼんやりと女を見る。 そのけだるさは行為による脱力だろうか、それとも女の隠された怪しい部分であろうか? いずれにせよ、朝もやの中にたたずむ女は圧倒的な輝きを持っていた。 彼の髪を撫でる仕草もまた妖艶で、男の神経を麻痺させる。 そして、月の光で輝いていた彼女も、夜明けを待つ彼女も、同じ彼女だ。 彼の愛を受けとめる唯一の存在で、なおかつ彼を愛するという点でも唯一の。 と、いう事は、この女は愛の女神か。 神は死んだと言う男の心の中に住む、ただ一人の神の化身なのか。 少なくとも、女はそうありたいと思っていた。 愛を教えるのは自分の役目であると。 そして、それは彼の心に届きつつあった。 返事の無い男だったが、女はそんな彼を笑顔で見守る。 閉じられた瞼の下では、きっと幸福な夢を見ているのだろう。 女は、その夢に自分も出ていればいいと願った。 そうすれば、目を閉じていても彼の心では自分を見ていてくれるのだろうから。 「あたしも、忘れない。ずっと・・・。」 彼を起こさぬよう、小さく声に出してみる。 そう、忘れる事は無いのだ。 彼女には、彼の姿は忘れる事が出来ない。 何があっても、彼の姿を忘れる事は無いのである。 たとえ彼女に、何があっても・・・。 辺りは一層明るくなってきた。 夜明けだ。 遥か彼方に見える地平線から光が差し、二人を照らす。 木陰の彼らにも枝と葉の間から光がさし込んで影を作った。 眠る男の頬を照らし、座る女をも明るく映し出す。 光は、今まで闇で見えなかった女の涙をみせつける。 女は男の寝顔を見つめていた。 例えようも無く幸福であろうこの時に、女は泣いていた。 それは静かで、そして穏やかな涙である。 その口が動き、音の無い音で眠っている男の名を何度も呼んだ。 夢にまで語りかけるようなその行為だったが、男は気がつかぬまま眠っているようだ。 それでも女は話しかける。 必死に彼の心に呼びかける。 まるで彼に呪文をかけるように。 恋に、どうしようもない恋に落ちているのは彼女の方だった。 その苦しさにもがいて息が出来ないのは、男ではなくて・・・。 日の出は美しかった。 その美しい光は、月と同様に彼らを祝福したのであろうか? 世界は彼らの生き方とは関係無く廻り続ける。 月や太陽も、そんなものかもしれない。 全ては、流れる。 1分、1日、1年、一人の人間が何を思っても止める事は出来ないのだ。 例えこの太陽を見つめる女が真摯に願ったとしても。 そして、時は流れる。 (←次章へ続く) |
