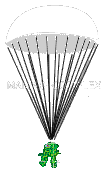 |
ドール写真館
P6
| 「じゃあ、それがご両親の出会いだったのね?」 年配の看護婦の言葉に、向いに座った若い看護婦は頷いた。 「今でも一緒に旅しているのを見て、何となく憧れちゃって。」 交代時間までの時間をくつろぐ彼女は、まだ馴染んでいないのか、時々下ろしたての白衣の裾をいじったりする。 「なんかいいですよね・・・。そんな風に誰かを元気にしてあげられたらいいなぁ、って。」 まだ幼さの残る口調で、遠くを見ながら呟く。 髪を束ねて白衣に身を包み、患者を助け。 新米ではあっても、患者にとっては彼女も一人の立派な看護婦である。 あの時、ホテルの一室で旅の男を診たあの時の彼女と同じように。 そこで、隣で一緒に話を聞いていたもう一人の若い看護婦が口を挟んだ。 「あれ、志望動機・・・あたしには白衣が着たいからって言ってなかった?」 同期の気安さからか遠慮無く笑う友人に、彼女は笑いながら抗議する。 「もう〜、せっかくいい話だったのに〜、台無しでしょう〜!」 「まあ、それも立派な動機かもね」 「ですよね!ほら〜。」 同意を得られた彼女は、友人を肘で突っつきながら意外と満足そうだ。 「さあ、そろそろ行きましょう。何処に将来の素敵な彼氏がいるかもしれないんだもの、仕事頑張ってね。」 「はい、頑張ります。」 そう言われた彼女は少し照れながら微笑む。 何を思っているのだろうか。 多分、さまざまな事が頭を駆け巡っているに違いない。 早足で歩く若い後姿には希望と、まだ見ぬものへの憧れが溢れ、そして窓から差す光にはあの誘いの人日と同じ春のぬくもりが満ち溢れていた。 終 |

終
・・・うーん、とっても長くなってしまいました。
ごめんね(^_^;)>ALL
では解説ページなど・・・。

←GO NEXT PAGE!

GO TOP! GO DOLL MENU!